子どものために購入する児童書を選ぶとき、「どの児童書を選べば良いかわからない」という経験をした方は多いでしょう。何百、何千とある児童書から、子どもの興味に合った本を探すのは難しいもの。児童書選びに悩みすぎて、購入する本を決められないこともあるかもしれません。
この記事では児童書選びに悩む方に向けて、児童書の種類や選び方を解説。おすすめの児童書も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
児童書の魅力とは?
児童書とは、乳幼児〜中学生に向けた本のこと。大人向けの本とは違い、子どもの読書に対する興味や読書レベルに合わせて作られています。
児童書は読んでいて楽しめるのはもちろん、子どもの想像力を養えるところも大きな魅力。想像力が豊かになることで、新しい視点からものごとを考えられるようになります。
また、児童書のシンプルで真っ直ぐなメッセージは、子どもだけでなく大人に刺さることも。児童書の魅力に触れ、思わずハマってしまう大人も少なくありません。
児童書の主な種類
児童書にはたくさんの本がありますが、種類としては下記の5つに分けられます。
- 絵本
- 児童文学
- 洋書
- 図鑑
- 学習漫画
絵本は主にイラストを中心に構成された本。しっかりした物語のある本から仕掛けつきの本までさまざまあり、0歳〜5歳向けの本が多いです。
児童文学は挿絵と文字を中心に構成されている本。挿絵がある分、文字を読むのが苦手な子どもでも楽しく読み進められます。
洋書は海外の言語で書かれている本で、ストーリーを楽しみながら英語も学ぶことも可能。このほか、生物や乗り物の図鑑、漫画形式で楽しく勉強できる学習漫画も定番の児童書です。
児童書の選び方
数多くの児童書から子どもに合った本を選ぶためには、子どもの年齢や好みを考えたうえで探すのが◎。ここでは、児童書の選び方のポイントをいくつか紹介します。
年齢・学年で選ぶ
児童書選びに悩むなら、子どもの年齢や学年を基準に選ぶのがおすすめ。選択肢が狭まり、子どもに合った本を見つけやすくなります。
以下では、低学年・中学年・高学年・中学生に分けて、向いている児童書の種類を紹介。ぜひ児童書選びの参考にしてください。
低学年
低学年には、挿絵中心で文字が少なめの児童書が向いています。
文字を習い始めたばかりの子どもにとって、文字の多い児童書は読みにくいもの。しかし、ページ数が少なく、サクサク読み進められるような挿絵中心の児童書なら、ストレスなく読書できます。
なぞなぞの本など、楽しめる要素の多い児童書もおすすめ。「読書は楽しいものだ」と感じてもらえる本を選ぶと良いでしょう。
中学年
小学校3・4年生の中学年には、ストーリー性の高い児童書を選ぶのも選択肢のひとつ。読書に慣れてきた中学年の時期なら、展開が読めないような凝ったストーリーも楽しめるようになります。
海外で人気がある作品や、シリーズ展開している作品もおすすめ。シリーズ展開している作品は続きが気になる構成が多く、読書をより好きになるきっかけ作りになるかもしれません。
高学年
理解力が高まった高学年の子どもには、深いテーマを扱った児童書がおすすめです。精神的にも成長している高学年は、作中の複雑な心理描写なども理解できる時期。登場人物に共感できるような要素がある場合は、作品に対してより深くのめり込めます。
ノンフィクションや科学など、子どもが関心を持つ分野の本を読むのも◎。文字が苦手な子どもでも、自分が関心を持つ本をきっかけに、読書を好きになってくれるかもしれません。
中学生
中学生には、学生を主題とした児童書や心に残る名作がおすすめです。学生を主題とした児童書は思春期ならではの悩みにやさしく寄り添ってくれる本が多く、児童書が悩みを解決してくれる糸口になることも。
また、中学生は考えさせられるようなテーマを扱う名作も楽しめる時期です。作者の想いが強く込められた作品や、読み終わったあとの余韻を楽しめるような作品を選ぶと◎。
子どもの好みに合わせて選ぶ

児童書を選ぶ際は、子どもの好みに合わせてあげることも大切。例えば、子どもが興味のある分野に関する図鑑や、スポーツが好きならスポーツをテーマにした作品など、好みに合わせてあげることで読書に対するハードルを下げられます。
普段本を読まないなら、ストーリーがかんたんでページ数が少ないものがおすすめ。軽く読める児童書は途中で挫折しにくく、最後まで読み進めやすいです。
青少年読書感想文全国コンクールの課題図書から選ぶ
青少年読書感想文全国コンクールの課題図書は「新たな知識が得られるか」「多くの感動を得られるか」といった観点で、専門家によって選ばれています。
また、低学年〜中学生の学年別にラインナップされているため、子どもの年齢に合わせて選びやすいです。
ロングセラーの作品から選ぶ
児童書はロングセラーの作品を中心に選ぶのもおすすめ。ロングセラーの児童書は大人が読んだことのある作品も多く、子どもとコミュニケーションを取るきっかけにもなります。
また、ロングセラーの作品は、シンプルに面白い作品や心に響く作品がほとんど。読書に関心の薄い子どもでも、きっと興味を持ってくれるでしょう。
児童書はフリマアプリ「楽天ラクマ」でも購入できる
児童書は書店だけでなく、「楽天ラクマ」でも購入が可能。「楽天ラクマ」はさまざまな商品が出品されているフリマアプリです。児童書も出品されており、定番から名作と呼ばれるものまで、数多くの本が揃っています。
書店で見つからない本を探すときや、シリーズ物の児童書をお得に揃えたい場合は特に便利。また、商品代金の支払時は楽天ポイントを利用できるため、お得に買えるメリットもあります。
おすすめの児童書20選
ここからは、低学年、中学年、高学年、中学生向けのおすすめ児童書を20冊紹介。人気で読みやすい作品を厳選したので、ぜひ児童書選びの参考にしてください。
低学年におすすめの児童書5選
低学年には、挿絵が多めで読みやすい児童書がおすすめ。ここでは、低学年に向いている児童書を5冊紹介します。
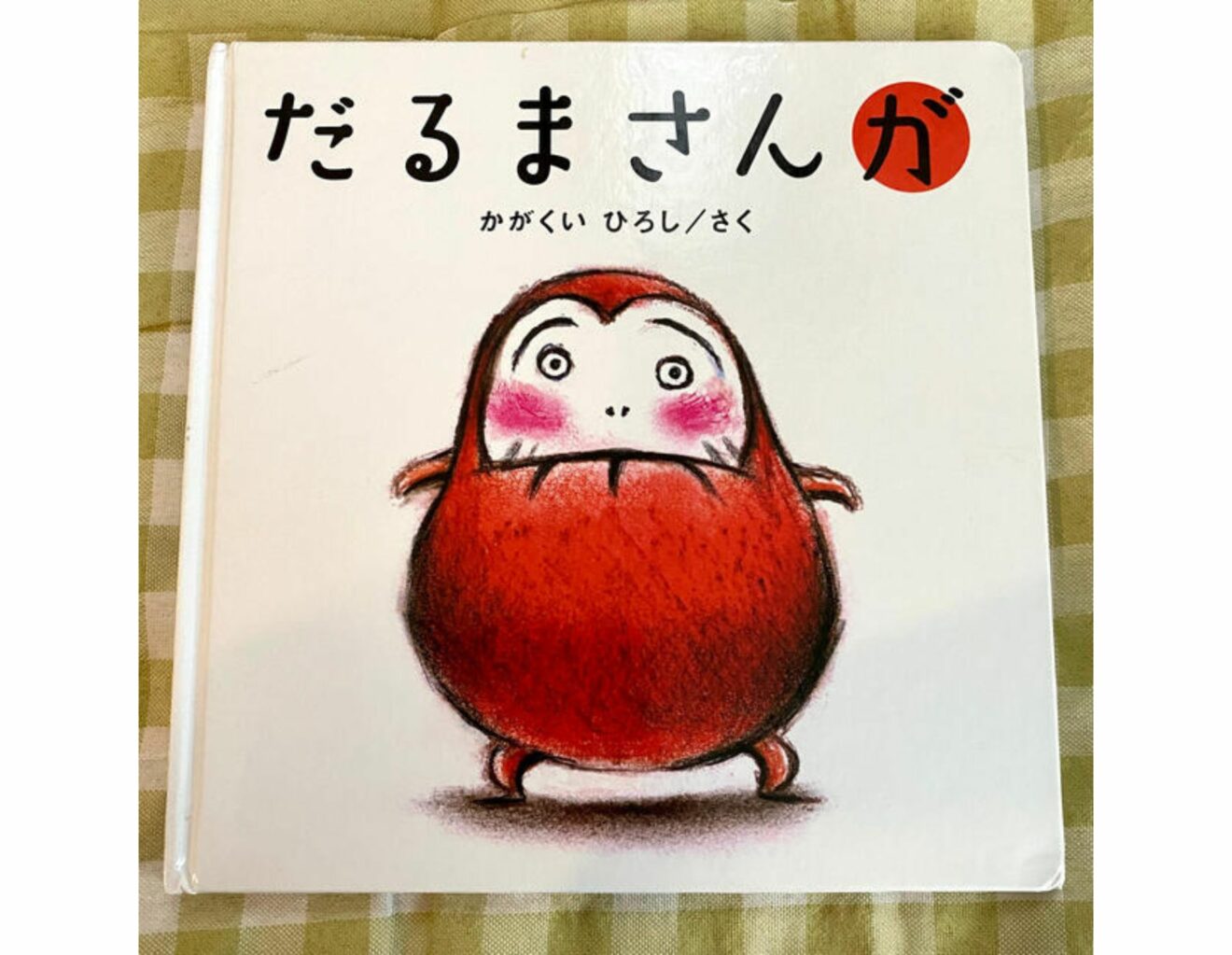
だるまさんが
『だるまさんが』は、子どもの遊びのひとつ「だるまさんがころんだ」をテーマにした絵本。「だるまさんが」のあとに、だるまさんが伸びたり、縮んだりと、ユーモラスな行動を取って笑わせてくれます。
だるまさんが取る奇想天外な行動は、子どもだけでなく、大人も思わず笑ってしまうほど。子どもと一緒に笑いながら読むことで、「読書は楽しいものだ」と感じるきっかけになるかもしれません。
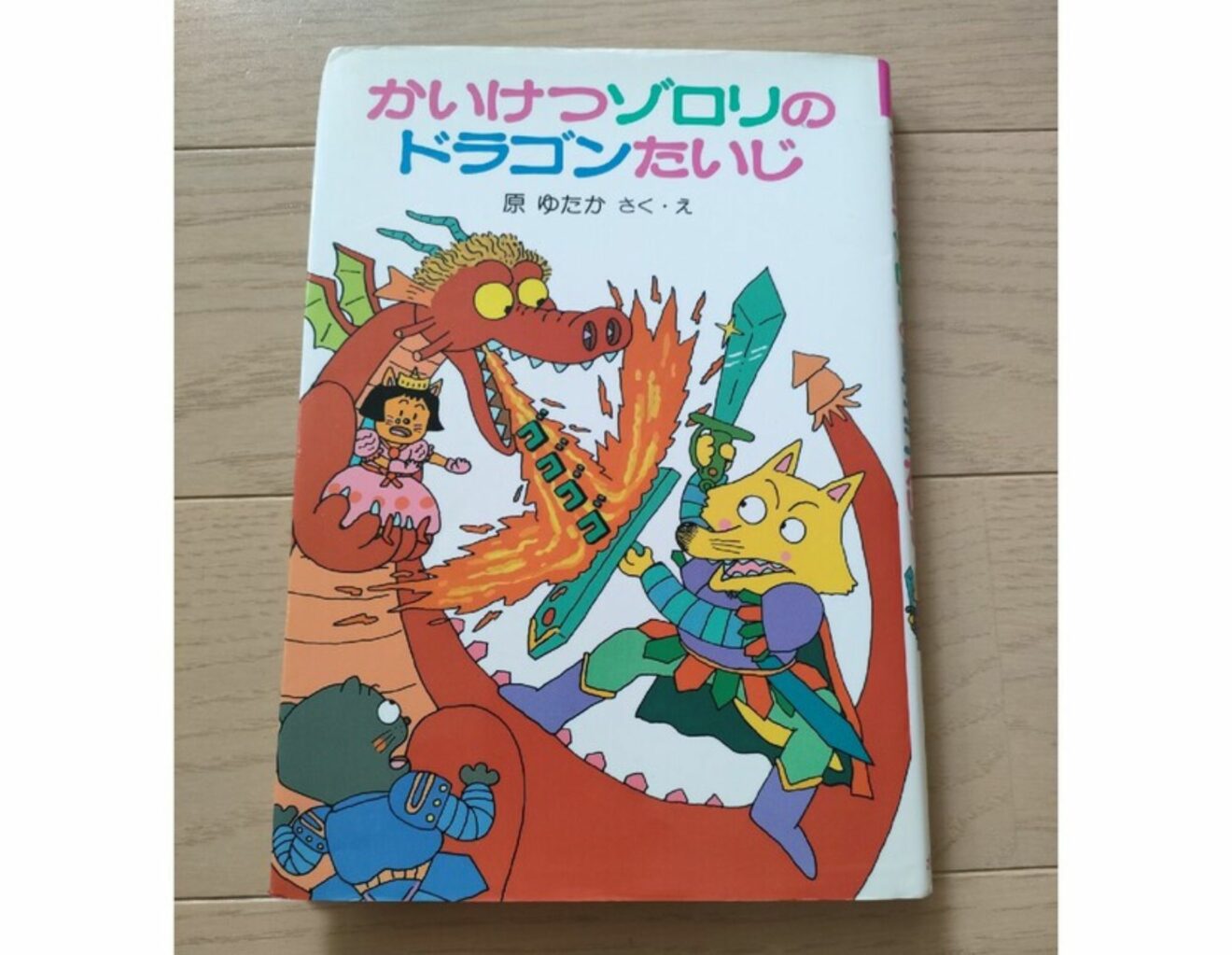
かいけつゾロリのドラゴンたいじ
『かいけつゾロリのドラゴンたいじ』は、1987年から続くロングセラーシリーズ『かいけつゾロリ』の最初の作品。主人公のゾロリが、お姫さまの花婿に立候補するために奮闘する物語です。
絵本に比べると文字は多めですが、楽しげな雰囲気の挿絵が多く、楽しく読み進められます。また、かいけつゾロリはアニメ化されたこともある作品。事前にアニメを視聴して興味を引いている場合は、読書が苦手な子どもでもすんなりと読み進められます。
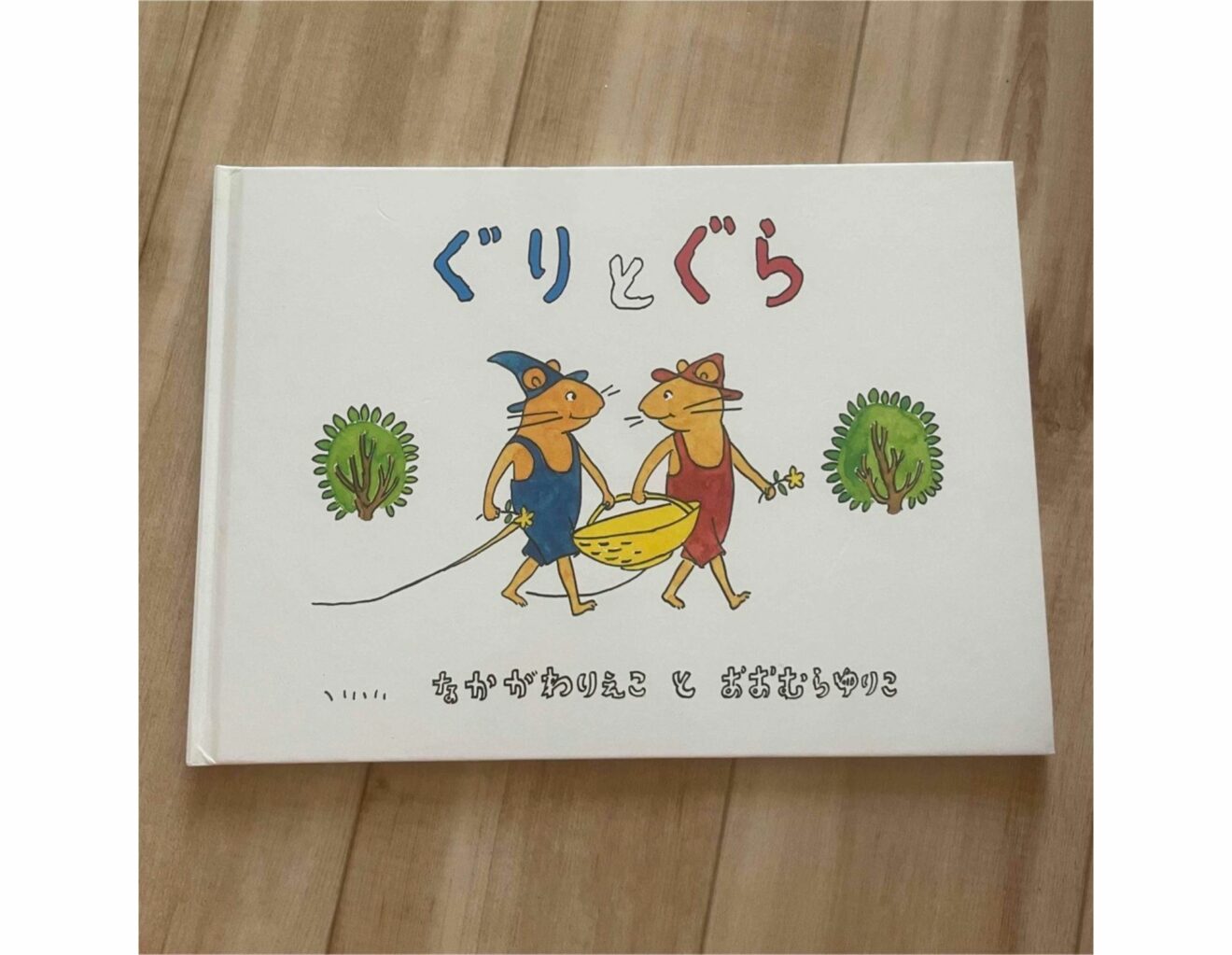
ぐりとぐら
『ぐりとぐら』は、児童書の定番とも呼べる大人気のロングセラー作品。ある日ぐりとぐらが見つけた大きな卵を使い、さまざまなハプニングを乗り越えながらカステラを作る物語です。
『ぐりとぐら』の大きな特徴は、思わず口ずさみたくなるようなリズム感のある文章。言葉が持っているリズム感を感じることで、言葉に対する興味や関心を高められます。
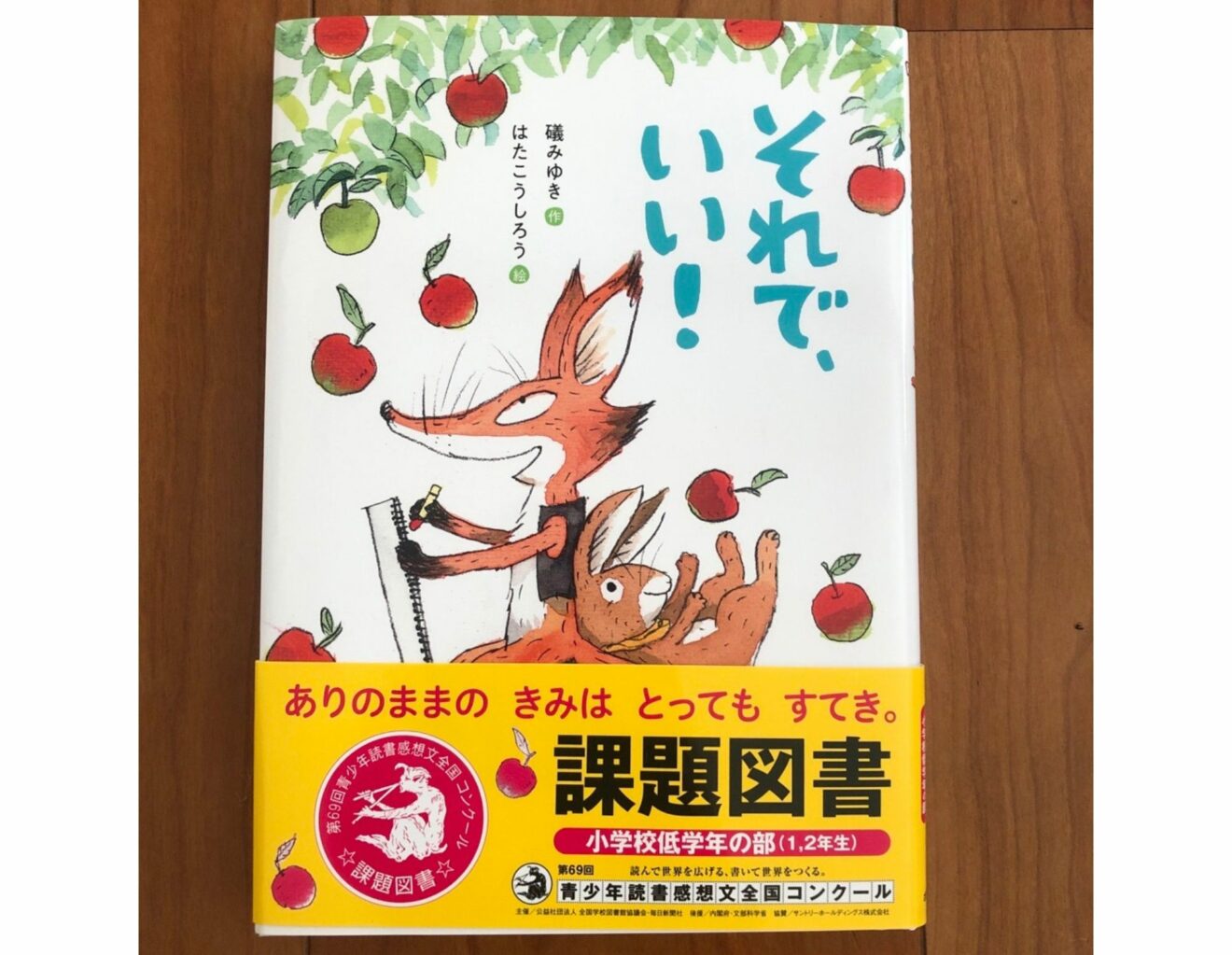
それで、いい!
『それで、いい!』は、絵を描くのが大好きなきつねを主人公とした物語です。あるきっかけで展覧会に絵を出品することが決まったきつね。最初は展覧会にすごい絵を出品するために意気込んでいましたが、絵に対する評価を気にしすぎてしまい、最終的に絵を描けなくなってしまいます。そんなきつねが、友だちをとおして大切なことを思い出していくストーリー。
「ありのままの自分で良い」というメッセージが詰まったこの作品は、「人の目を気にして好きなことができない」といった子どもの悩みにやさしく寄り添ってくれます。
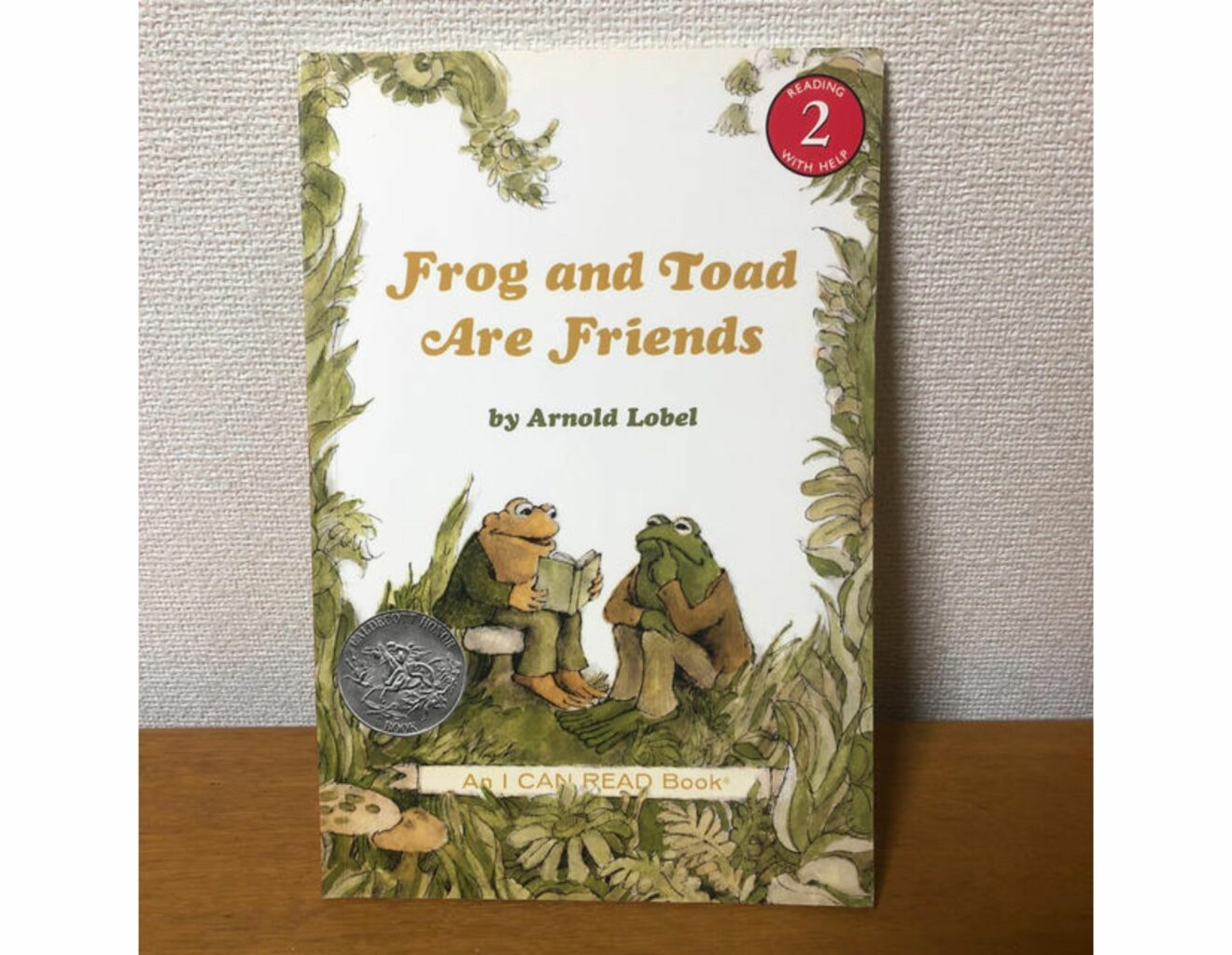
Frog and Toad Are Friends
『Frog and Toad Are Friends』は、仲の良いカエル「がまくん」と「かえるくん」の友情を描いた物語。日本版は『ふたりのともだち』というタイトルで、国語の教科書にも掲載されました。
英語版は文章の量が多いため、まずは簡単な英語を理解してから読むのがおすすめ。日本版を一度読んで文章の内容を把握し、見比べたり翻訳したりしながら英語版を読み進めるのも良いかもしれません。
中学年におすすめの児童書5選
続いて、中学年におすすめの児童書を5冊紹介します。
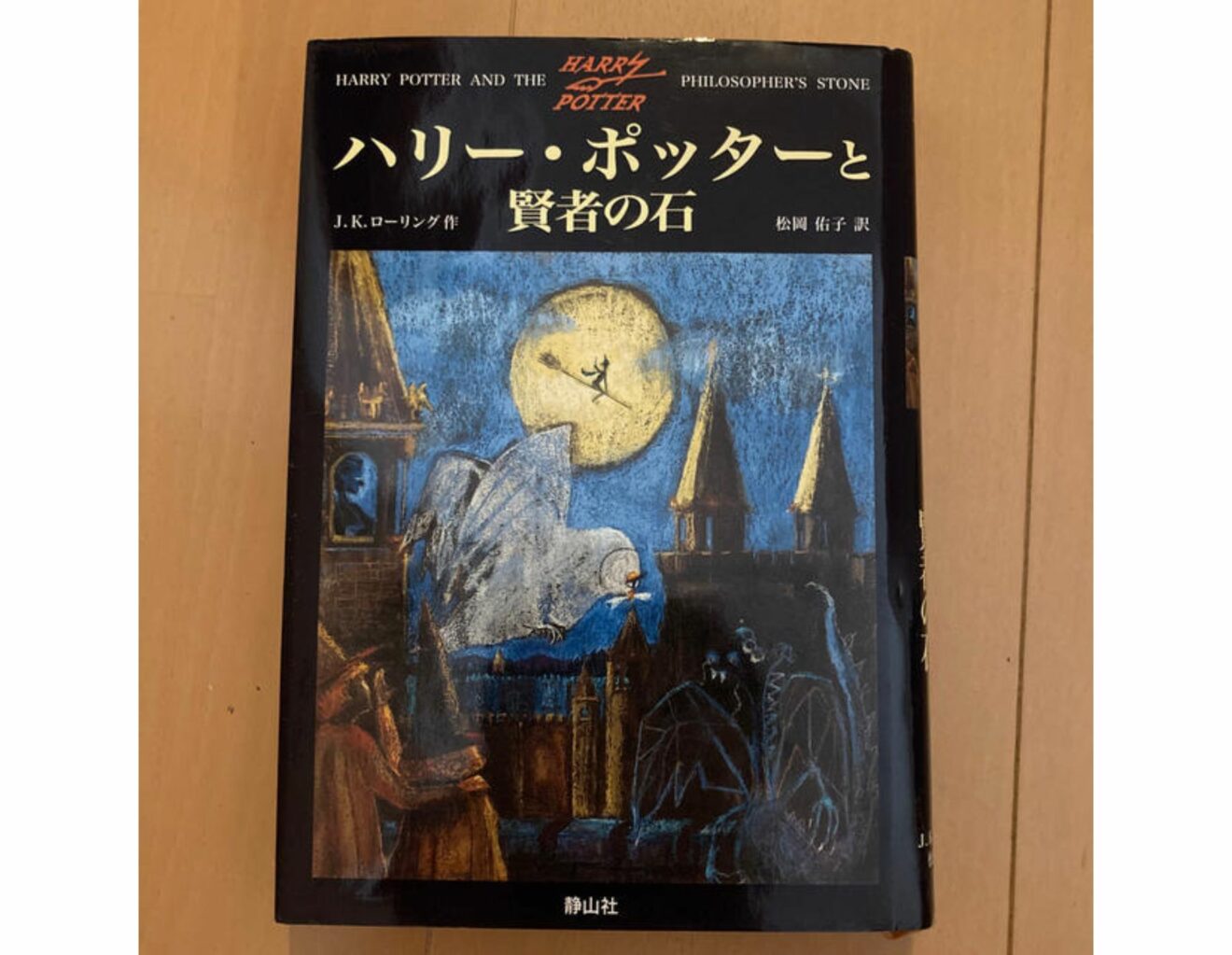
ハリー・ポッターと賢者の石
『ハリー・ポッターと賢者の石』は、世界的な人気を誇る大ヒット作品『ハリー・ポッターシリーズ』の1作目にあたる児童書。主人公のハリーがとあるきっかけでホグワーツ魔法魔術学校に入学し、さまざまな事件に巻き込まれながら魔法使いとして成長していく物語です。
ほとんどは文章で構成されており、作品内の挿絵は少なめ。しかし、想像力を掻き立てられるような表現なので、文章を読むだけで頭の中にハリー・ポッターの世界観がスッと入ってきます。子どもの想像力を養いたい方には特におすすめの1冊。
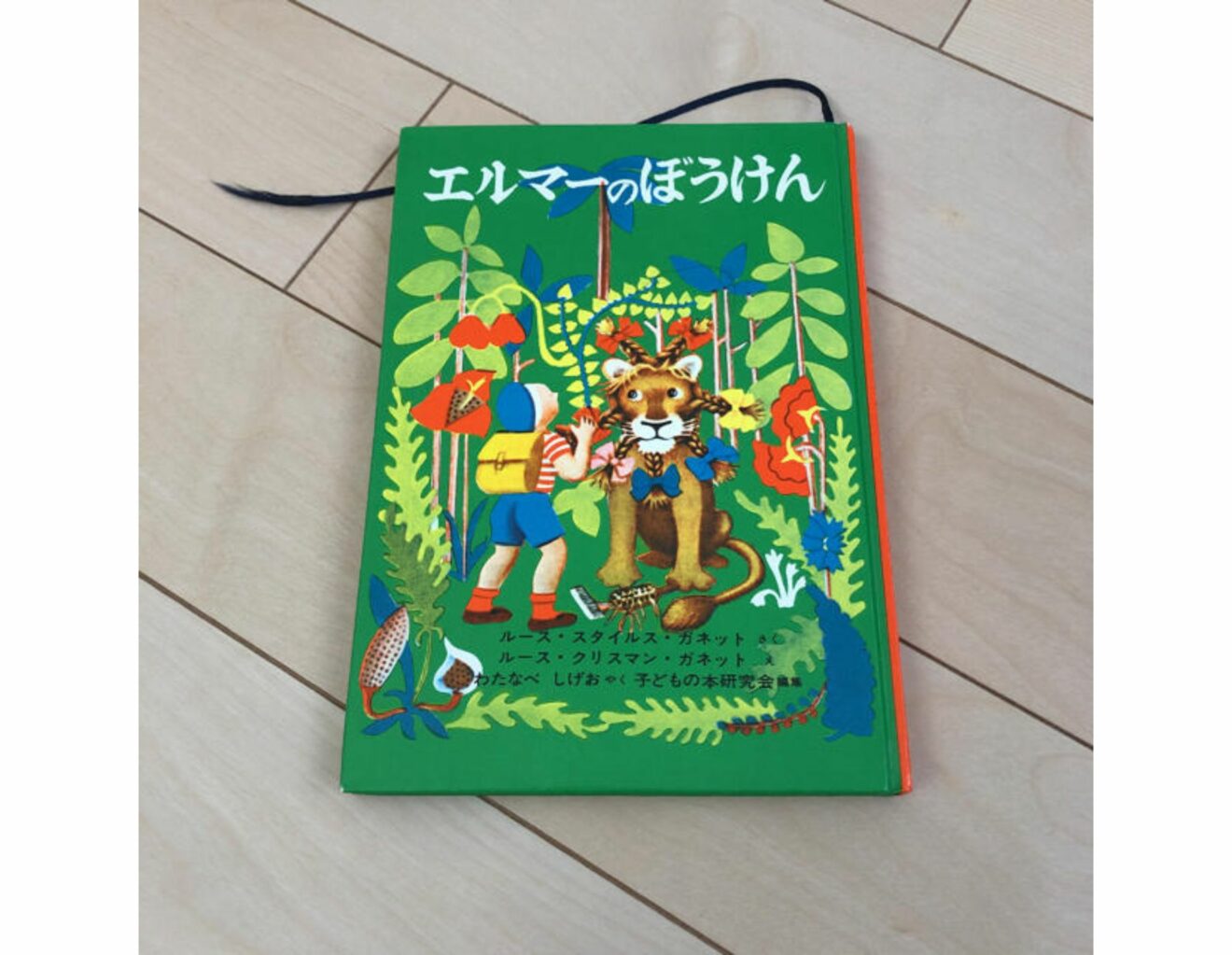
エルマーのぼうけん
『エルマーのぼうけん』は、主人公のエルマーがどうぶつ島に囚(とら)われているりゅうの子どもを助けるために奮闘する冒険物語。リュックに入っていた輪ゴム、チューイングガム、歯ブラシなどを使って、どうぶつ島の恐ろしい動物たちに対処していきます。
ハラハラするような展開の連続で、思わず読み進めてしまう構成が特徴。続きが気になるストーリー構成なので、読書が苦手な子どもも挫折せず最後まで読みやすいです。
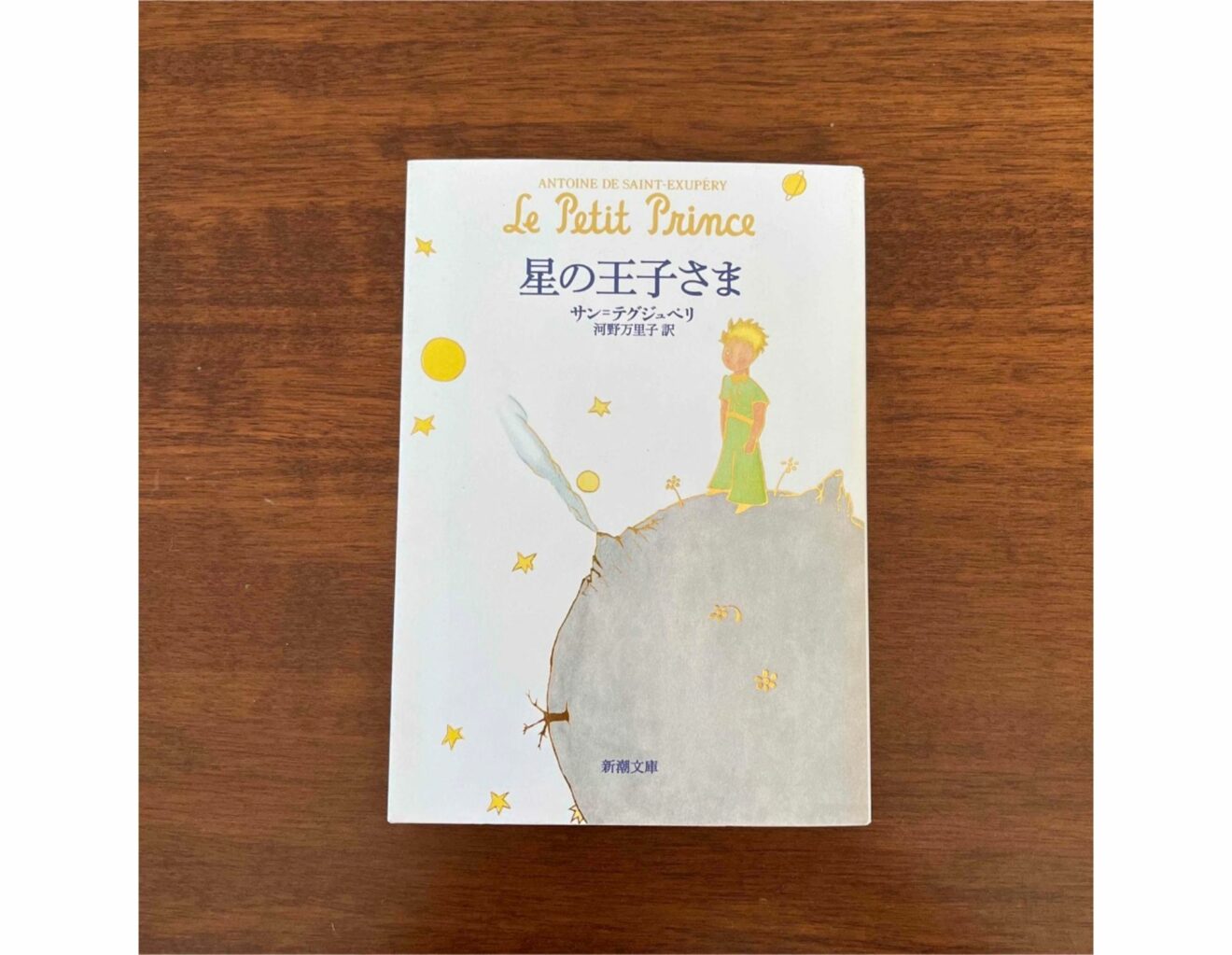
星の王子さま
『星の王子さま』は、1943年に発売されたベストセラー作品です。砂漠に不時着した飛行士の前に突然あらわれた不思議な少年は、実はいくつもの星を巡って地球へと降り立った王子さま。飛行士は、王子さまが旅で訪れたさまざまな星の話を聞いていきます。
「大切なものは目に見えない」という、重要なことを教えてくれる1冊。生きるうえで教訓になるような名言も数多く散りばめられています。
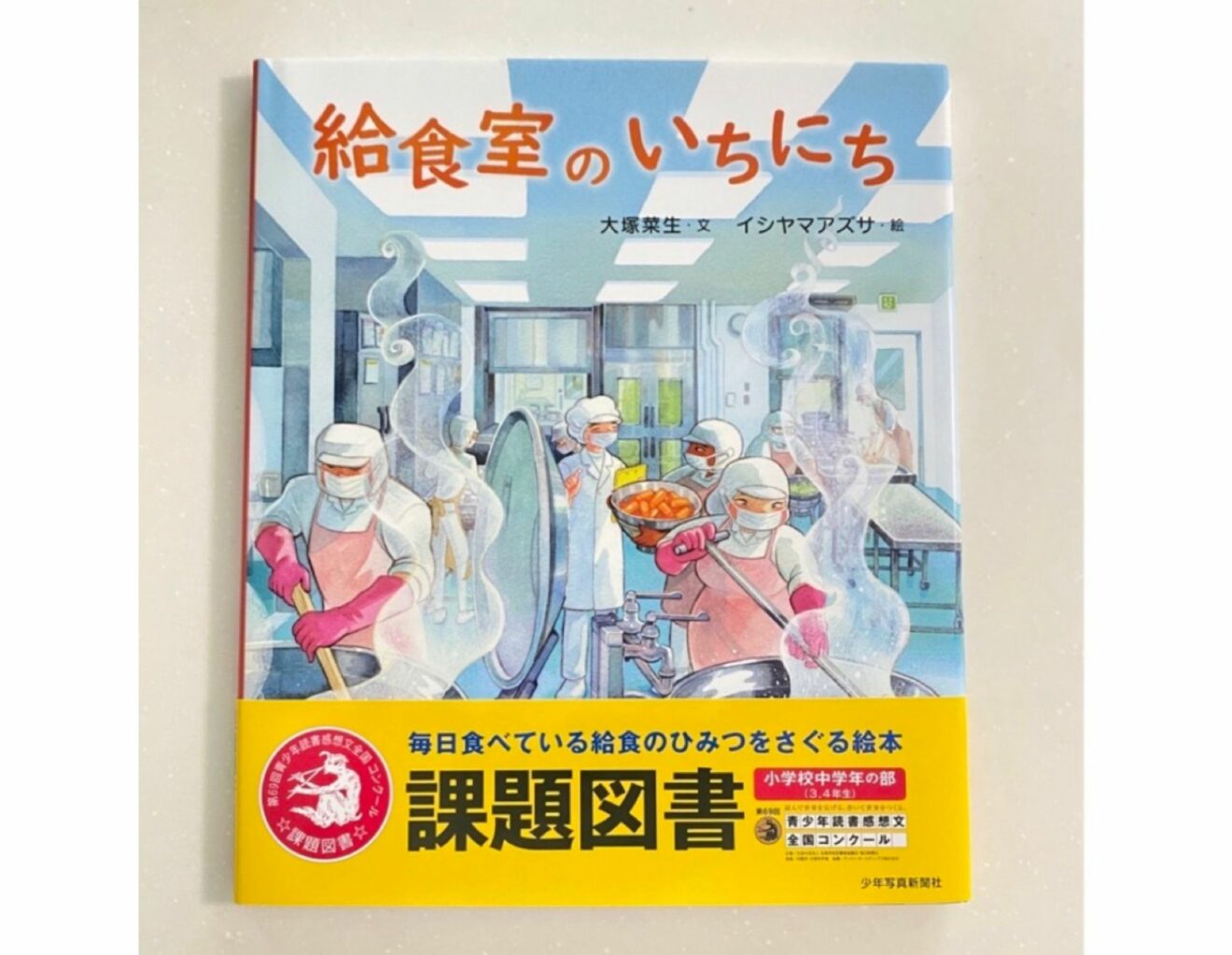
給食室のいちにち
『給食室のいちにち』は、病院の給食室で勤務した経験のある作者の体験をもとに、給食室の現場を再現した絵本。身支度から調理、献立の決定まで、給食ができるまでの過程がわかりやすく描かれています。
「給食室では何をしているの?」「たくさんの給食をどうやって作っているの?」という子どもの素朴な疑問を解消できる1冊。物事に取り組むときの役割分担、段取りの重要性も学べます。
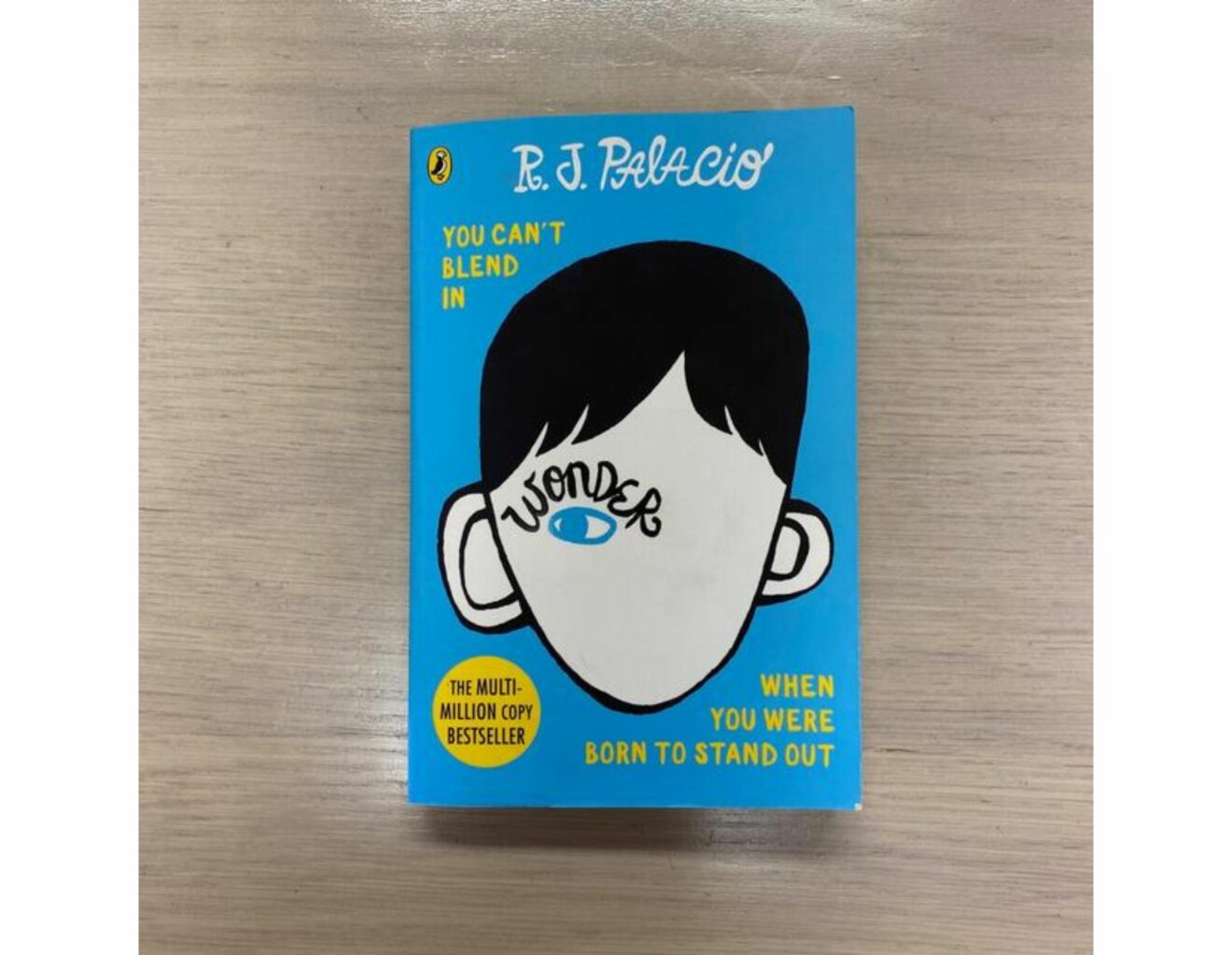
Wonder
『Wonder』は2016年に課題図書に選ばれた人気作です。生まれつき顔に障害のある男の子「オーガスト・ブルマン」は、10歳から初めて学校に通うことに。周囲の生徒に怖がられたり、いじめられたりする中で、オーガストは家族や先生、友だちと大切な絆を育んでいきます。
一人称の語り手が各章で変わっていくのが『Wonder』の特徴。各キャラクターの心情に寄り添いつつ、共感しながら読み進められます。
高学年におすすめの児童書5選
高学年には、文章を主体とした児童書や深いテーマを扱った本がおすすめ。以下では、高学年におすすめの児童書を5冊紹介します。
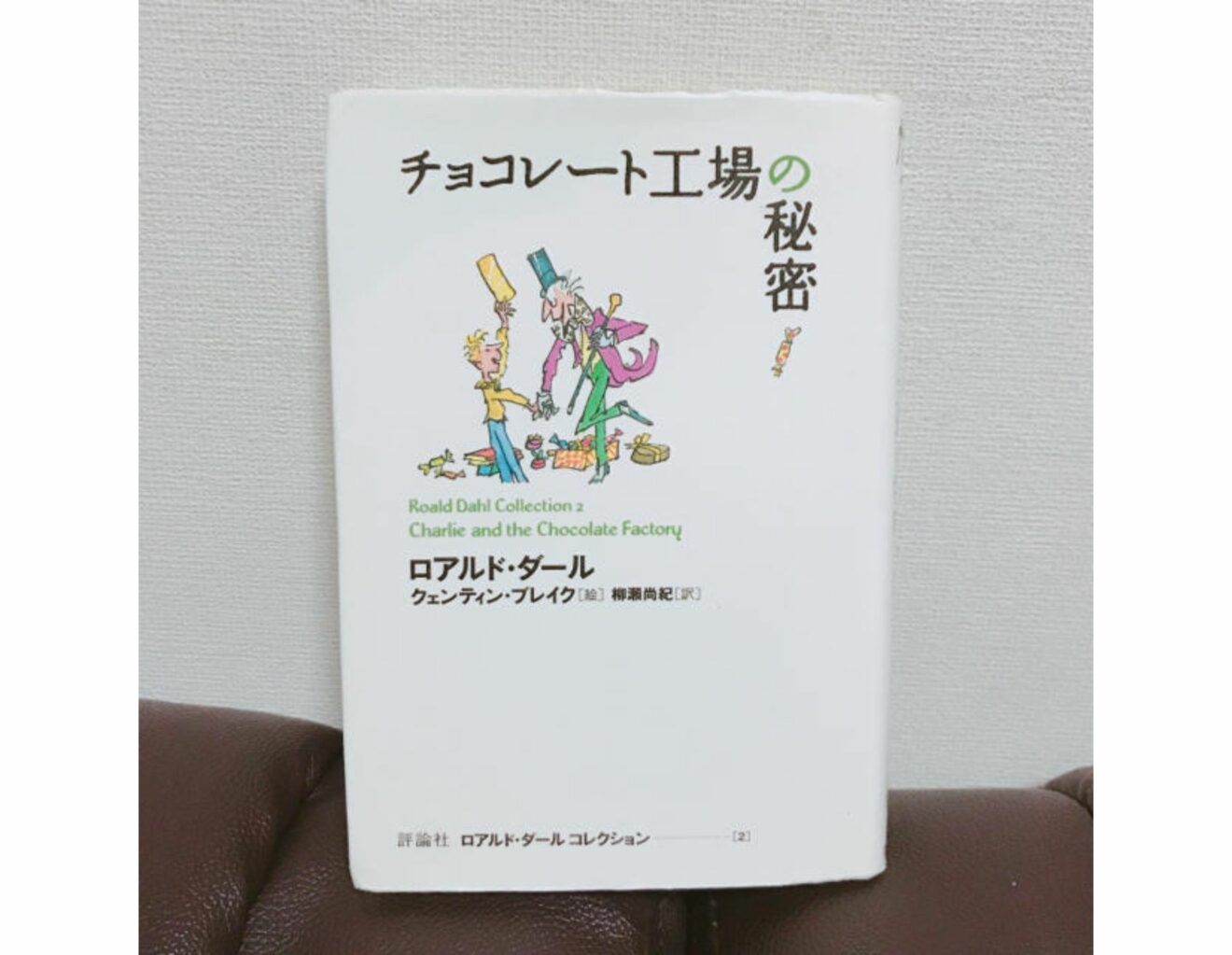
チョコレート工場の秘密
『チョコレート工場の秘密』は、大ヒット映画『チャーリーとチョコレート工場』の原作にあたる児童書です。チャーリーの住む街にあるチョコレート工場は世界一有名でありながら、働いている人の姿を誰も見たことがない謎だらけの工場。そんなチョコレート工場に、5人の子どもたちが招待される物語です。
チョコレートを主題にした本作は、お菓子好きな子どもなら楽しく読み進められるはず。家族の大切さを学べる本でもあります。
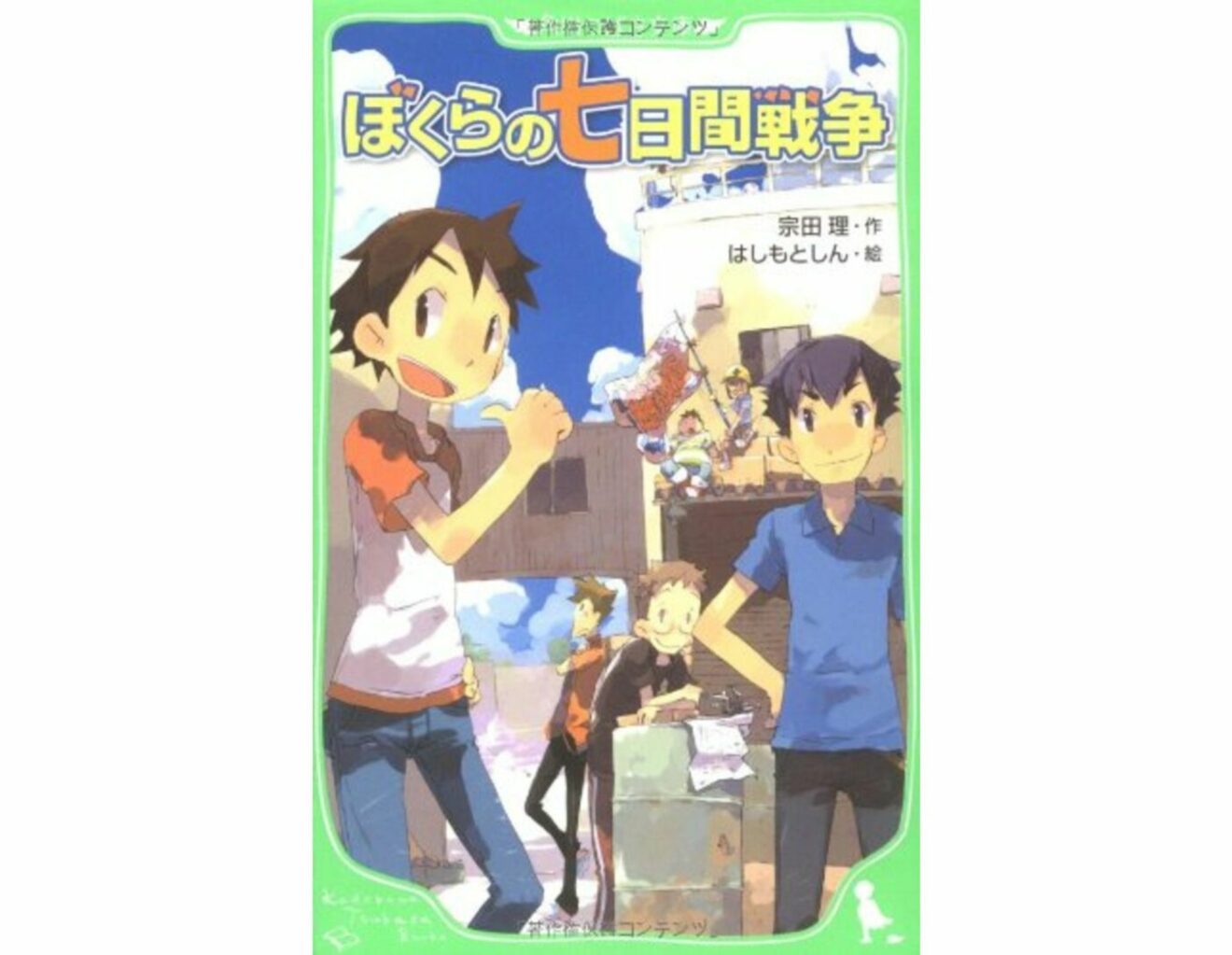
ぼくらの七日間戦争
『ぼくらの七日間戦争』は、人気のベストセラー作品『ぼくらシリーズ』の1作目です。東京下町にある中学校、1年2組の男子生徒全員が河川敷の廃工場に立てこもり、この場所を「解放区」として大人たちに反乱。そんな子どもたちと大人たちの大戦争の様子を描いた作品です。
子どもの自己主張の大切さ、仲間と団結して協力する力、そして、問題に対して考える力や創造的な解決策の重要性を伝えています。
ストーリーはワクワクするような展開の連続。飽きることなく読み進められるため、本を読む習慣のない子どもでも楽しめます。
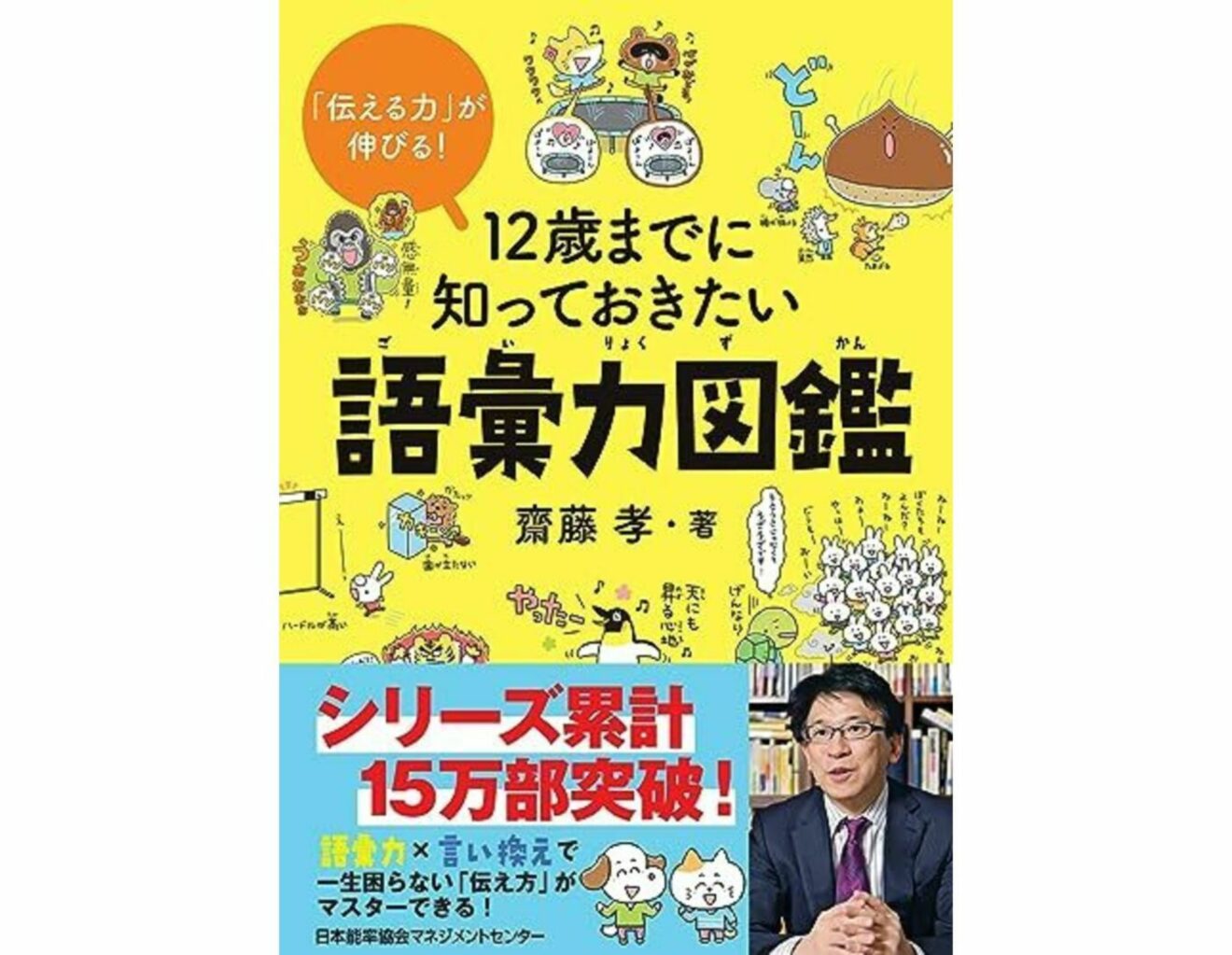
12歳までに知っておきたい語彙力図鑑
『12歳までに知っておきたい語彙力図鑑』は、感情を表現する言葉をわかりやすく解説した図鑑です。子どもを含んだ若年層は「やばい」など、短い言葉で感情を表現しがち。しかし、短い言葉だけでは正確な意思疎通が難しく、大人になって苦労する可能性もあります。
こうした問題を解決してくれるのがこの図鑑。文章とイラストを使って、感情表現に使う言葉やポジティブな言葉にいい換える方法を解説してくれます。
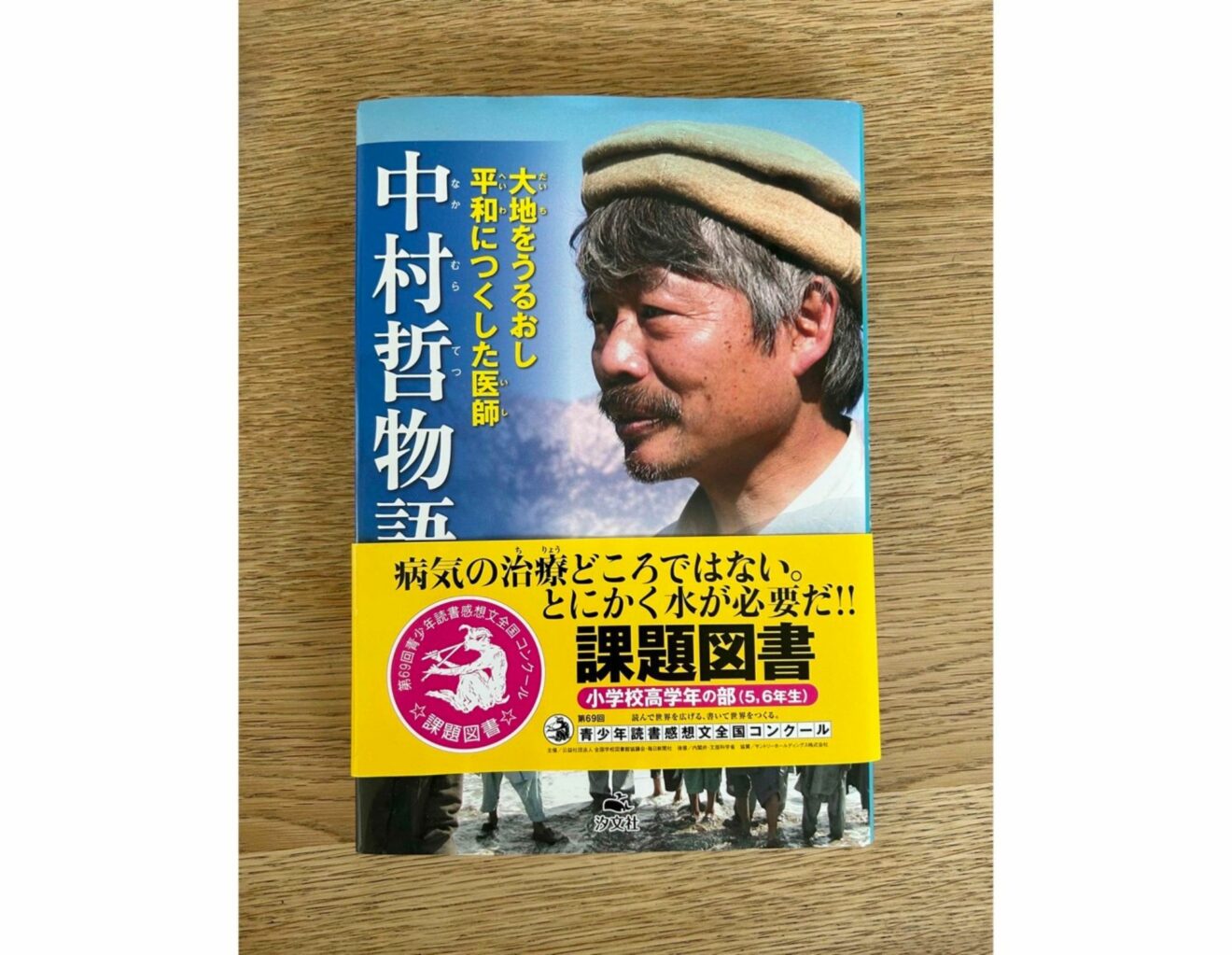
中村哲物語
『中村哲物語』は、パキスタンやアフガニスタンで医療支援を行っていた医師「中村哲先生」の伝記。2023年には、高学年向けの課題図書にも指定されました。
飢餓によって次々に命を落とす子どもたち。そんな子どもたちを前に井戸を掘ったり、用水路を作ったりしながら、懸命に命を守るための活動を続けた様子が記録されている本作からは、「命の大切さ」や「本当に大切なことは何か」を学べます。
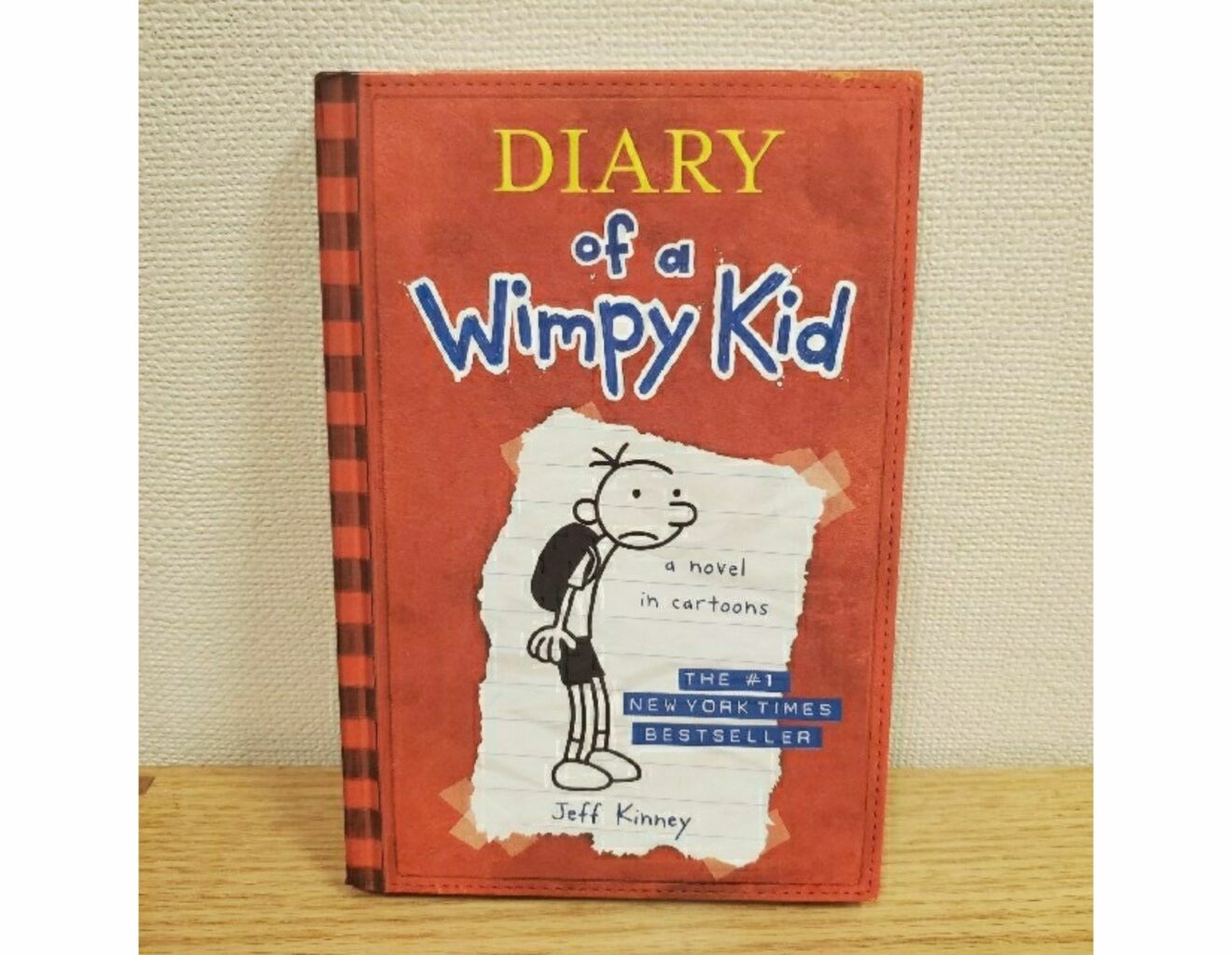
Diary Of A Wimpy Kid
『Diary Of A Wimpy Kid』は、海外の小学生から大人気のシリーズ作品。「人気者になりたい」「お金持ちになりたい」「モテたい」など、さまざまな願望を持つグレッグの毎日がコミカルに描かれています。
日本版タイトルは『グレッグのダメ日記』。その名のとおり日記形式で物語が描かれているのが特徴で、サクサクと読み進められます。子どもの英語の学習にも◎。
中学生におすすめの児童書5選
最後に中学生におすすめの児童書を5冊紹介します。
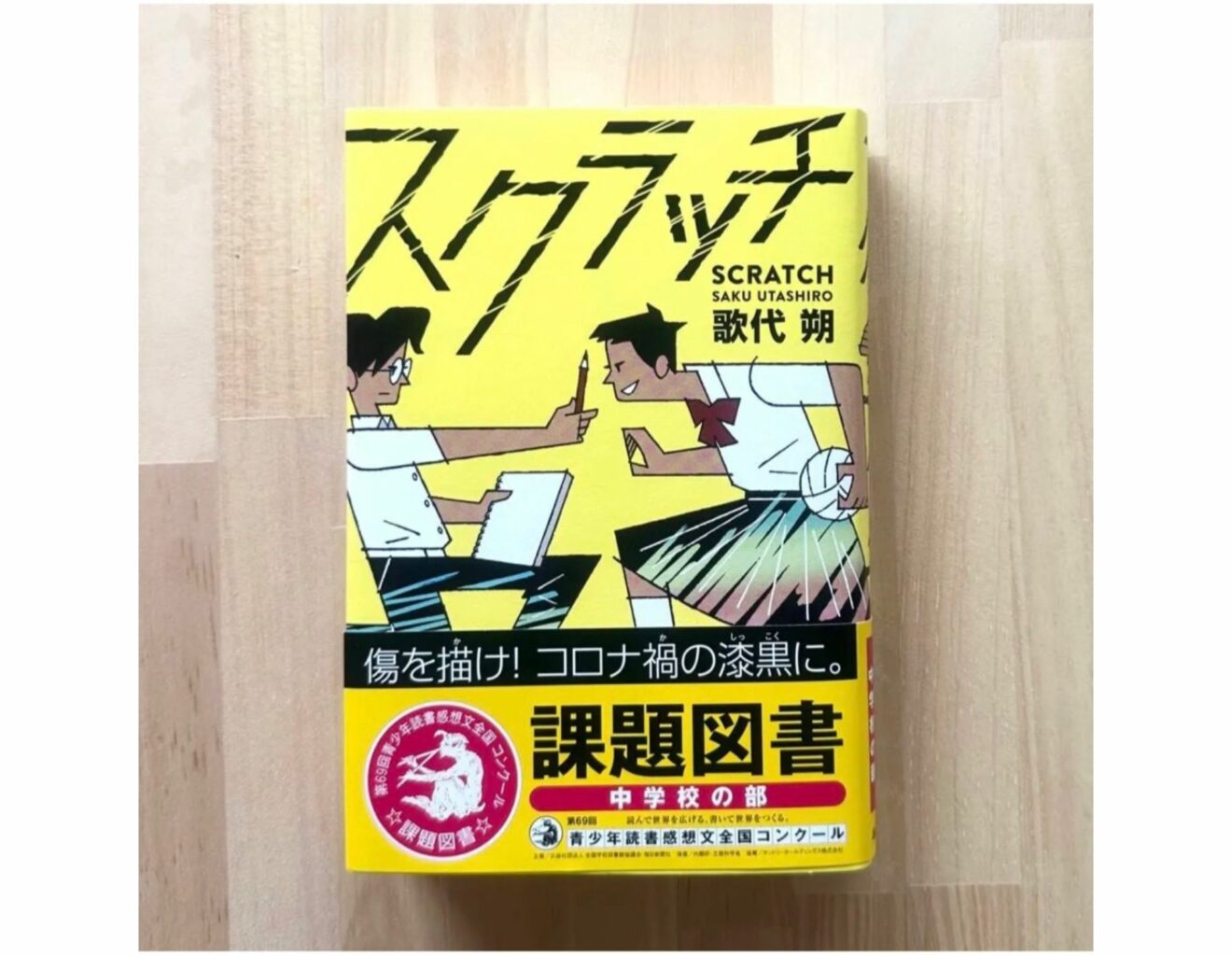
スクラッチ
『スクラッチ』は、コロナ禍で学生生活を送る中学生の青春物語。感情豊かな「鈴音」と常に平常心を保っている「千暁」の2人を中心に、中学生ならではのリアルな悩みや自分らしい在り方を探し求める姿が描かれています。
作中で描かれる登場人物の心情や悩みは、現実の中学生なら共感できること間違いなし。中学生向けの課題図書にも選ばれています。
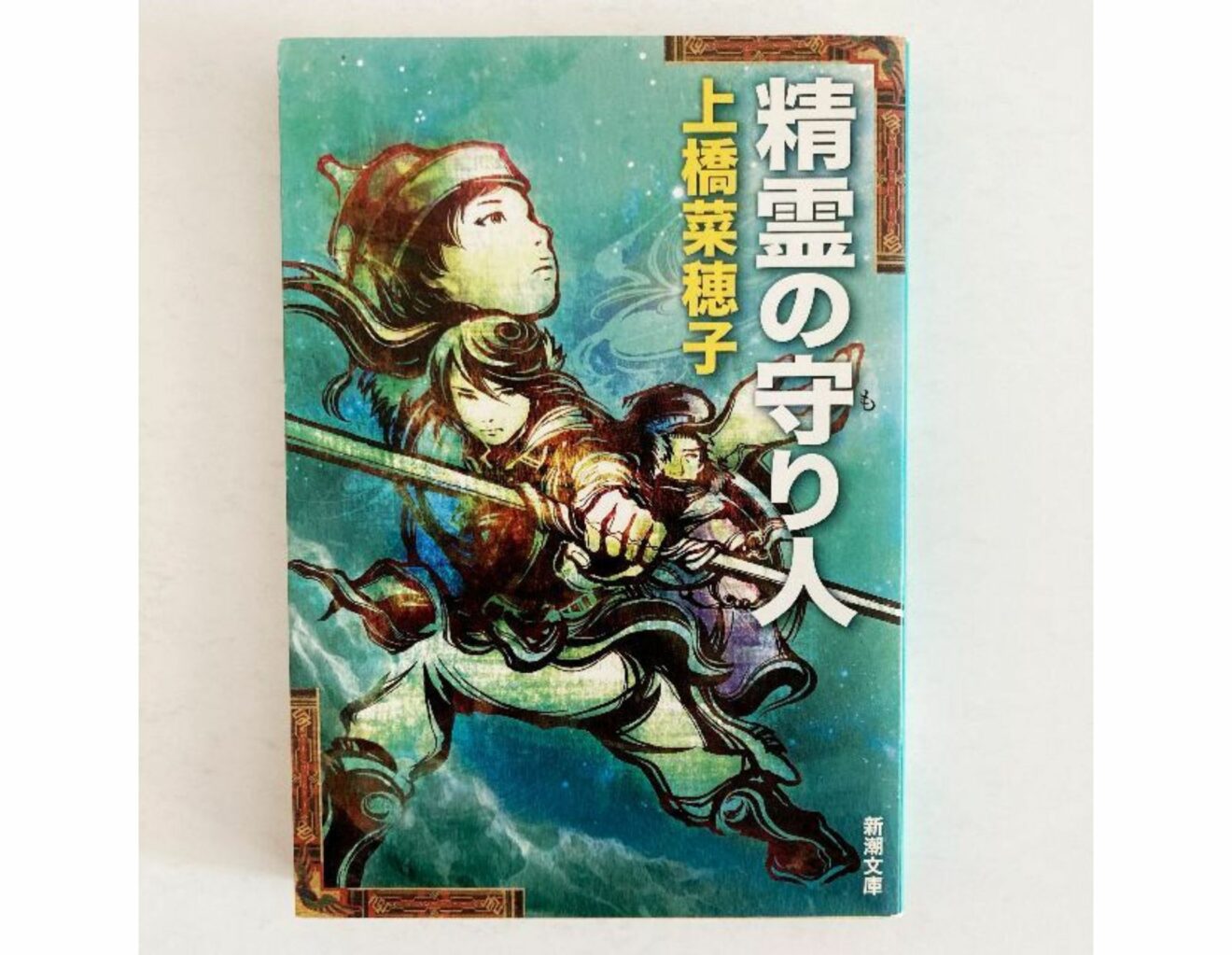
精霊の守り人
『精霊の守り人』は、10巻と外伝3巻からなる『守り人シリーズ』の第1作です。舞台は人の世と精霊たちの世が混在するファンタジー世界。女用心棒「バルサ」が、新ヨゴ皇国の皇子を守るために奮闘する物語になっています。
ファンタジー作品ならではの独特の世界観は、子どもの想像力を大きく養ってくれるはず。子どもが興味を持ってくれたら、シリーズを揃えるのも良いかもしれません。
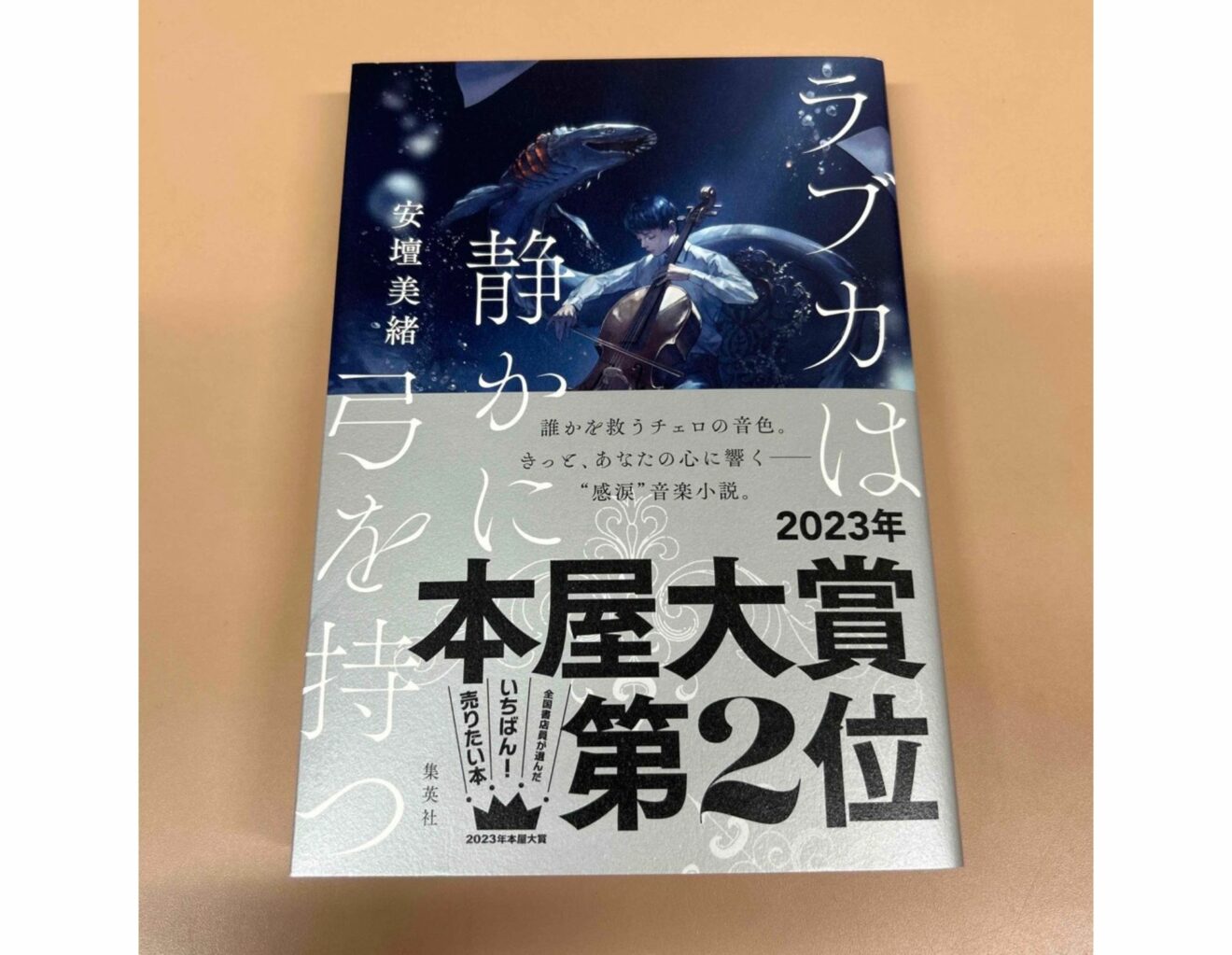
ラブカは静かに弓を持つ
『ラブカは静かに弓を持つ』は、スパイと音楽の要素を組み合わせた作品。スパイとして活動する橘は、著作権法の演奏権を侵害している証拠を掴むため、音楽教室への潜入調査を命じられます。しかし、そこで出会った講師や仲間との出会いが橘の運命を変えていく物語。
橘の心情の変化がていねいに描かれており、どんどん読み進めたくなるような内容になっています。また、スパイ小説としてのスリリングな展開も魅力。子どもから大人まで楽しめる人気作品です。
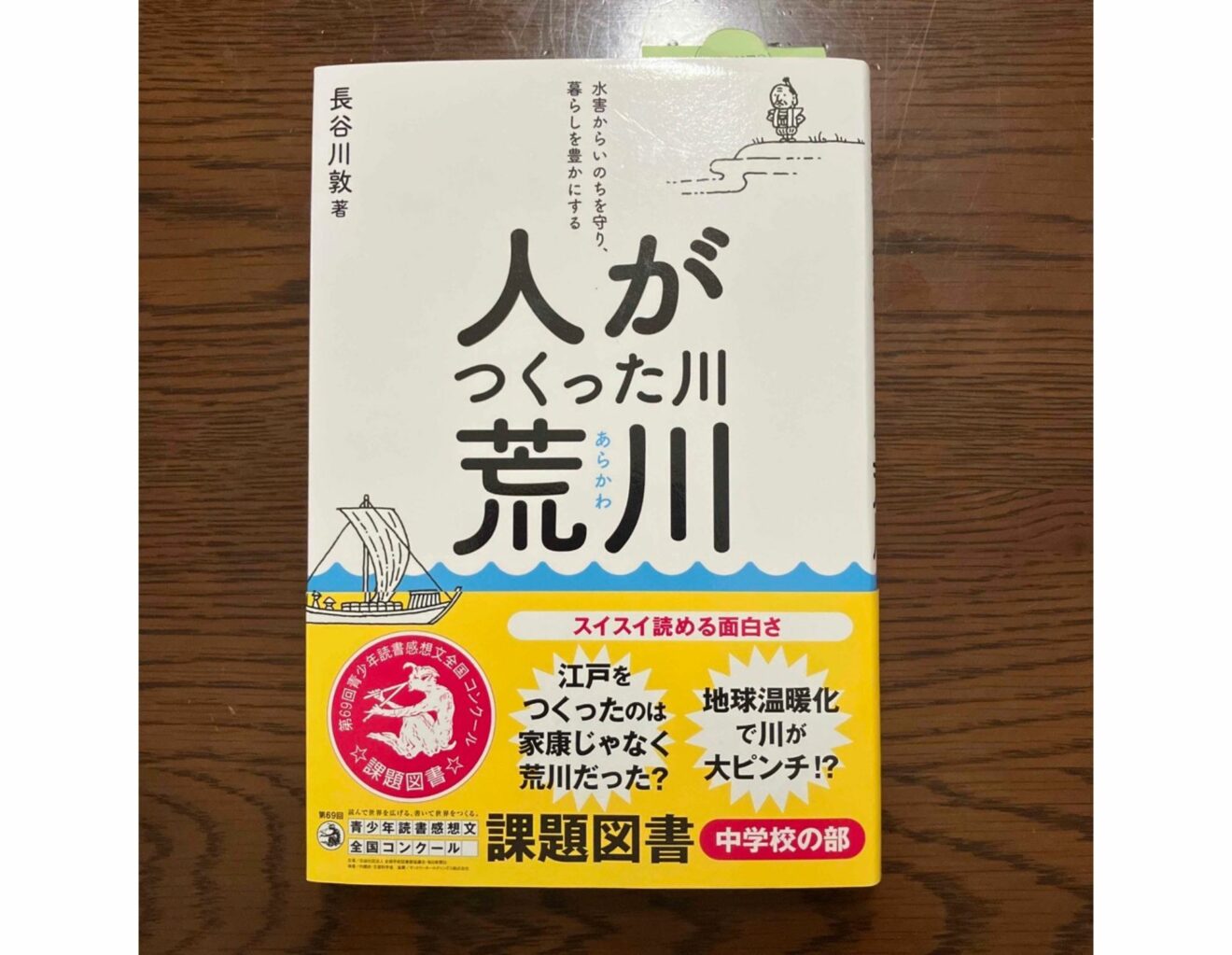
人がつくった川・荒川 水害からいのちを守り、暮らしを豊かにする
『人がつくった川・荒川 水害からいのちを守り、暮らしを豊かにする』は、2023年の課題図書に選ばれた作品。埼玉・東京を流れる荒川の歴史を振り返りながら、水害の深刻さや対策などをわかりやすくまとめた1冊です。
中学生向けの課題図書ということもあり、本の読みやすさは抜群。環境問題に対する関心を高めるきっかけにもなるでしょう。
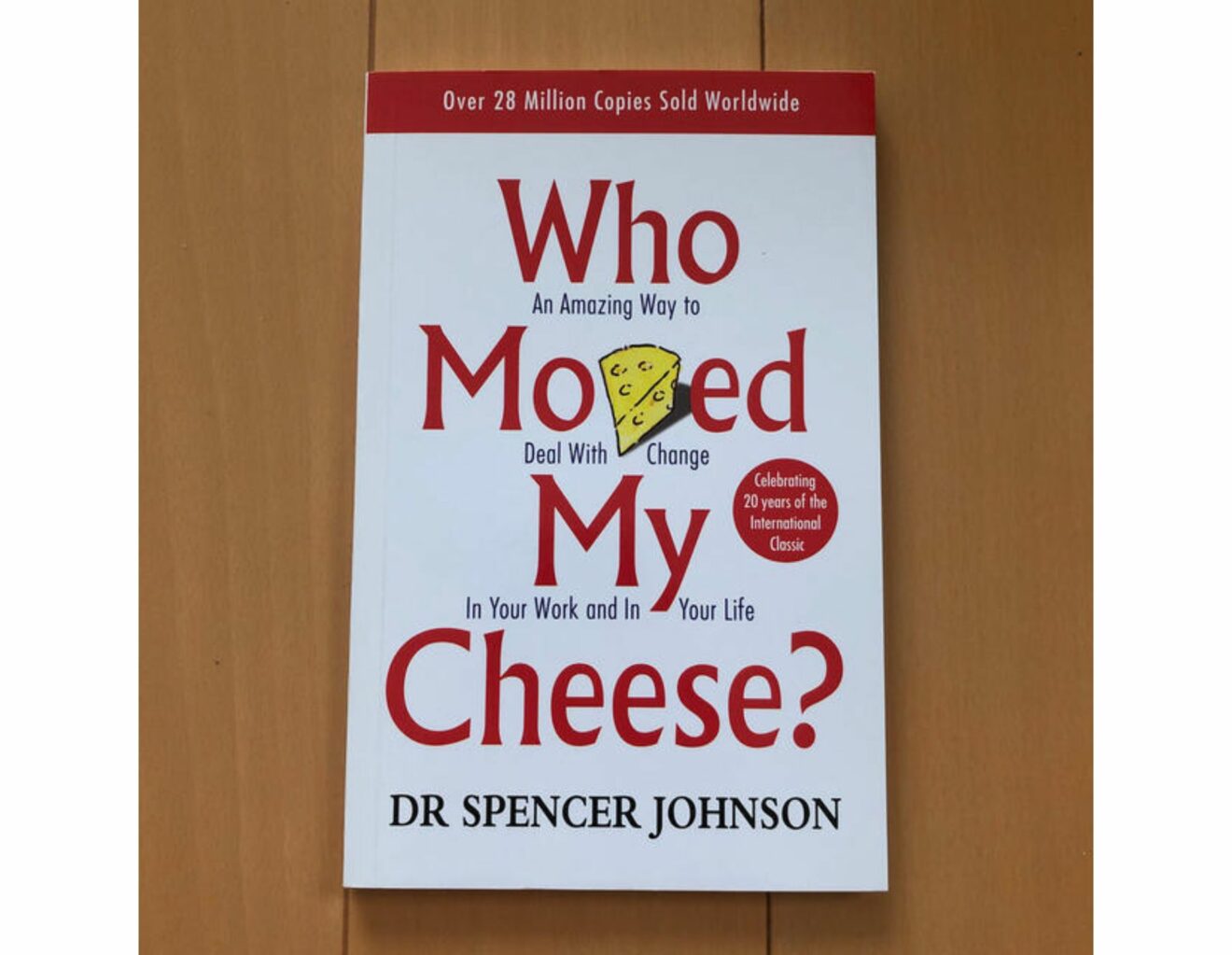
Who Moved My Cheese?
『Who Moved My Cheese?』は、世界的ベストセラーの童話です。2匹のネズミと2人の小人が、突然消えた大量のチーズを探す物語。ビシネス書としても有名で、各国のトップ企業が社員教育のために本作を採用しています。
ストーリーで主に学べるのは、変化を怖がらずに挑戦する大切さ。内容は短く、中学生でも無理なく読み進められるボリューム感になっています。
まとめ
たくさんの児童書から子どもに合った本を探すには、子どもの年齢や好みを考慮することが大切です。また、読書が苦手な子どもには、興味がある分野の本を選んであげるのもあり。児童書選びに悩むときは、課題図書やロングセラーの作品もチェックすると良いでしょう。
シリーズ物の児童書をお得に揃えたいなら、フリマアプリの「楽天ラクマ」が便利。児童書探しの際は、ぜひ「楽天ラクマ」を覗いてみてください。






